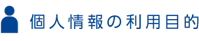【薬剤師の職場を解剖】調剤薬局と病院の違い
2025.04.30
【来院見学や面接のご応募はコチラ】

こんにちは!チームここはじの葉山なつです🍀
みなさんは、今年のGWをどのようにお過ごしでしょうか?
今年のGWは飛び飛びの祝日なので、私は日帰りの外出で「食べる・食べる・動く」くらいのペースで楽しみたいと計画しています📝
さて今回は、薬剤課の特集記事第二弾!
ここ数年では薬局が増設傾向にあるそうです。
ドラックストアに併設されている薬局もよく目にするようになりました。
もちろん求人も薬局だらけ…
そんな時代だからこそ、病院勤務に!
もっと言うと湘南第一病院の薬剤課の魅力をお伝えし、「病院で働いてみたい」「興味が沸いた!」と思ってもらえるよう、特集記事を立ち上げました。
第二弾は「調剤薬局と病院の違い」をテーマにしました。
今回は薬剤師の採用活動を通してチームここはじメンバーが得た気づきから記事を作成してみました。
湘南第一病院の薬剤師という仕事や職場との比較も必見です👀とくとご覧あれ🌟
前回までの記事をまだ見ていないよという方はこちらをお見逃しなく☝
Q1:役割の違いとは?
そもそも「調剤薬局」と「病院」では、薬剤師の役割が違うことに気づきました。
具体的にいうと、「調剤薬局の薬剤師」は調剤や服薬指導を通して、患者の薬物療法の安全性を確保し、チーム医療に貢献する役割があるといわれています。
一方で「病院の薬剤師」は、同じ調剤や服薬指導であっても領域が広く、副作用のモニタリングや処方提案を含め、薬物治療に参画しチーム医療に貢献します。
ちなみに湘南第一病院の薬剤師は、入院診療(病棟)、外来診療・訪問診療というそれぞれの機能に、薬剤師を配置しています。
それぞれの機能により、関わる他職種やユーザーが異なりますが、求められている役割は同じです。
他の病院さんと異なる点としては、「高齢者」つまり患者本人だけでなく、そのご家族や支える高齢者施設の職員もユーザーと定義していることです。
したがって、それぞれのユーザーにとって、適切な薬物治療に寄与することが求められます。
そのため当院薬剤師の役割は以下のように考えています。
①高齢者の薬学的管理を行う
②高齢者の適切な薬物治療への参画
③適切な訪問診療のバックアップ
採用広報としては、病院の薬剤師は調剤薬局に比べ仕事の領域が広がりますが、当院は「高齢者医療」に限定して深めていける職場だと感じています。
そのため当院は一般的に病院の薬剤師の仕事とされている「がん化学療法」や「治験業務」はありません。
また高次機能病院ではないので「救命救急業務」もありません。
これまで病院薬剤師の経験のない薬剤師さんにも、比較的チャレンジしやすい病院だと考えています🏥
Q2.患者様(対象者)の違いとは?
さて2つ目にあげたのは、患者様にも違いがあるなと感じました。
患者層ではなく、患者様の状態が違うというのが適切かと思います。
調剤薬局を利用される患者様は、比較的病状の安定している患者様ということになります。
なぜなら対象者の方は、在宅や介護施設でお過ごしの方であるからです。
したがって一人の患者様と長く関わることができることが特徴です。
一方で病院に受診・入院される患者様は、状態を安定させるために来院されます。
つまり患者様の治療そのものに参画できることが特徴です。
したがって患者様との関わりは、病院の機能にもよりますが「状態が安定するまで」といえます。
ちなみに、湘南第一病院に限定して患者様について、もう少し詳しくご紹介していくと…
入院される患者様は大半が高齢者施設に入所されている要介護高齢者の方であり、状態の安定を目指して入院しています。
一方で受診される患者様は、地域住民の方も多いです。
院外処方となり調剤薬局に繋がる、病状が安定されている患者様もいらっしゃいます。
また診療科は、内科・循環器内科・消化器内科・整形外科・皮膚科を掲げています。
入院診療(病棟)では、ご本人さんが要介護高齢者ゆえに、意思表示が困難な方も少なくありません。
他職種と協力しながらご本人にとってベストな薬物治療について模索していくことができること。
退院後の患者様の訪問診療で他職種から、患者さんの様子を窺い知ることができること。
つまり、湘南第一病院は一人の患者様に長く関わることができること、治療に参画できること。
どちらの側面も持ち合わせています。
採用広報では、当院薬剤師の仕事を「やりがいや面白みは、アナタ次第で大きく広がる」と考えています。
自身の仕事が何に繋がっているのか…
それを想像しながら仕事をした分だけ、やりがいを見出すことのできる職場だと思っています。
Q3.他職種連携の違いとは?
湘南第一病院では、「どの職種も同価値」という考え方をもっています。
もちろん、診療における指示命令系統は変わりありませんが、資格の有無やレア度に関わらず対等であるべきだと考えています。
まだまだ組織としては、未熟な部分もありますが、目的に忠実に意見を交わし合える関係性を目指しいる組織です。
Q5:必要な知識の違いとは?
これは様々な捉え方ができますが、調剤薬局では、調剤報酬や保険薬局のルール、それらが定められている健康保険法などの知識習得が必要になります。
算定上必要になる側面もありますが、患者様への説明ができることが求められます。
近年は調剤事務という資格や職種が徐々に浸透しつつありますが、その役割は薬剤師のサポートであるため、必要な知識であることは変わりません。
一方、病院の場合は、算定は医事課(医療事務)が行います。
昨今、医療機関も機能分化が進み、病院のなかでも所属するセクションや与えられた役割によって必要な知識も異なります。
共通するのは、薬剤の専門家としての知識・診療のサポートを期待されているということです。
ちなみに当院では専門職の生涯学習を後押しするための評価制度も設けております。
半期に1度、学習内容を提出し、学習したことをどのように仕事に還元していくか面談を行い、評価しているのだそうです。
以上、チームここはじがお届けする「調剤薬局と病院の違い」でした。
初めての試みでしたが、みなさまいかがでしたでしょうか。
今回の取材で、他の病院や調剤薬局との違いを見出すことで、初めて知る当院薬剤師の職場や仕事がありました。
まだまだ「知らないこと」がたくさんあるのだと気づかれ、有難い機会をもらったなと感じています。
当院の薬剤師についてもっと知りたい方は、過去記事をチェック!
募集要項はこちらをチェック!
来院見学や面接をご希望の方はこちらをチェック!
インスタグラムでも当院の様子を公開しています☆
どうぞお見逃しなく☝