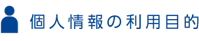高齢者医療に特化した急性期病院のリハビリテーションとは?
2025.05.23
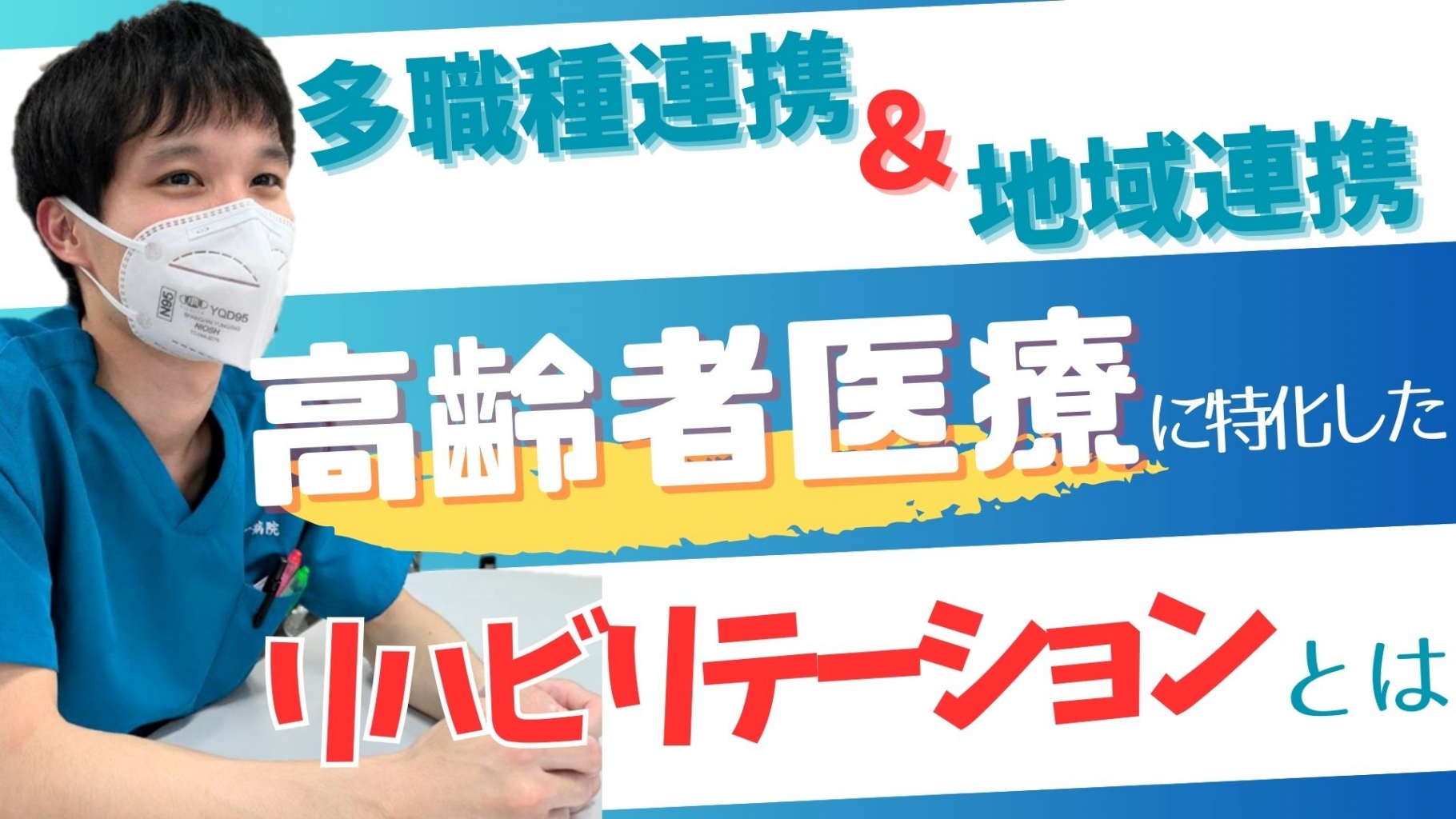
こんにちは!チームここはじの平塚陸です💨
GWは帰省したのですが、親戚の子供たちと1日遊んだら翌日には全身が筋肉痛に。
日頃の運動は大切だと実感しました…葉山さんにならい、僕もランニングでも初めてみようかな💭
さて今回は、初のリハビリテーション課特集記事‼
セラピストを目指すきっかけは多岐に渡ると思いますが、その中でも多いのは自身や家族のケガや病気の際にお世話になった。
スポーツを通じて興味を持ったという話をよく聞きます。
若年層のリハビリテーションと当院が行う高齢者のリハビリテーションは大きく異なり、興味関心を持ちづらい領域だと考えました。
そこで湘南第一病院のリハビリテーションの魅力を深堀して、高齢者のリハビリテーションに参画する仲間づくりをするべく特集記事を立ち上げました。
第一弾の今回は「当院のリハビリテーションと他職種連携・地域連携」をテーマにしました。
リハビリテーション課の結城リーダーと現場で働いている職員2名にインタビューを実施!
高齢者のリハビリテーションから、リハビリテーション課の職場まで、様々な角度でその魅力を聞いてまいりました。
本記事では、こんなことをご紹介していきます。
・当院のリハビリテーション課はどんなチーム?
・他院との違い!当院の考える高齢者のリハビリテーション。
・自信があります!他職種連携のリアル。仕事として、職場としての魅力。
・病院でそこまでできるの?セラピストと地域連携。その魅力。
それではさっそくお届けしてまいります‼
【当院のリハビリテーション課】
平塚:
ここはじメンバー同士のインタビューって妙な緊張感があるんですよね(笑)
結城リーダー!本日はよろしくお願いいたします🎤
まずは、当院のリハビリテーション課について教えてください!
結城:
こちらこそ。今日はよろしくお願いします!
当院のリハビリテーション課の構成は、理学療法士12名(内非常勤2名)とリハ助手が2名、コミュニケーター1名が在籍しています。
高齢者医療と聞いて、よくベテラン層ばかりのチームと思われるのですが、わりと若い世代のスタッフが多く、和気あいあいとした雰囲気が特徴的です。
経験歴としては、回復期や急性期を経て入職したスタッフもいれば、新卒から当院で勤めているスタッフも多く在籍しています。
【当院のリハビリテーションとは】
平塚:
院内のなかでも一番若手の多いチームですよね👀✨
続いて、当院のリハビリテーションについて教えてください。
やはり他の病院さんとの違いなどもあるんでしょうか。
結城:
『リハビリテーションの目的は機能回復ではなく、生活回帰とする』
まずはここが他院のリハビリテーションとの考えの違いになると思います!
当院の入院患者様はほとんどが要介護高齢者(要介護1~5)です。
近隣の有料老人ホーム、特別養護老人ホーム(一部老健やグループホーム、サ高住、自宅)から入院になる方がほとんど。
急性期病院としての役割を担っているので、平均在院日数は2週間ほど。
その中でも可能な限り元の生活に戻れるような状態に近づけて退院できるよう日々リハビリテーションに取り組んでいます。
平塚:
まず、対象患者の違いがあるということですね。
だからこそ、リハビリテーションの目的が異なると💡
結城:
そうなんです。もっと言うと、要介護高齢者のなかでも、病院にお越しになる=治療が必要な方であり、人生の最終段階に近い方が多くいらっしゃいます。
もともとの活動性・認知機能の低下がある方、重複障害を持っている方がほとんどです。
さらに具体的に当院のリハビリテーションがどのようなものか説明すると…
『その人らしい暮らし・最期まで人間らしい暮らしの実現』を意識し、“疾患”という側面のみではなく生活している“人”として捉え、一人ひとりの価値観を尊重しながら、生活全般にわたり支援をすることだと考えています。
例えば、高齢者の捉え方ですが、
入院した病気を持った人ではなく、長い人生を生きてきた人。と捉えています。
「入院」という人生の中の一瞬の単位ではなく「人生」という単位で捉えることで、その人が望む生活の質を模索できるのではないかと考えています。
平塚:
“人”として捉える…
当たり前のことだとは思いますが、疾患や機能面に偏りがちというのは、専門職あるあるだなと思います(;^_^
だからこそ敢えて言葉にしているということですね‼
結城:
平塚君、今日は冴えてますね(笑)
あとは、考えの比重が【機能訓練<生活回帰】であることも当院リハの特徴です。
要介護高齢者=機能回復が難しい。認知症があり機能回復が難しいなんて思ったことのあるセラピストは多くいると思います。
ですが私も湘南第一病院へ来てみて、機能訓練が進まなかったとしてもリハビリテーションを提供する目的がたくさんあるなと実感しています!!
そしてそんな中でも機能訓練を進めるためのしくみ(ケアユニット+他職種から集まる情報)が当院にはあります。
【当院の他職種連携】
平塚:
ケアユニットは前記事で僕も学んだことがあります。
まだ読んでない方はこちらをご覧ください!
当院の生活回帰のリハビリテーションやそれを実現するためのケアユニットというしくみを知ると、「他職種連携」が非常に重要だと感じました。
ここからは入院患者のリハビリテーションを担当しご活躍されているセラピストの一人。
前田さんに「他職種連携」をテーマに色々お話を聞かせてもらいます‼
まずは、院内のどのような職種と連携を図っているのでしょうか?
前田:
同じ病棟にいる看護師や主治医となる医師はもちろんですが、同じ課のコミュニケーターをはじめ、地域連携課の医療相談員(メディカルコーディネーター)とも多く関わりを持ち連携を図っています。
平塚:
他職種と連携を図ることについて、率直にどう感じているか教えてください!
前田:
自身は、理学療法士として働くのは湘南第一病院が初めてです。
学生の頃は、患者とセラピストの1対1でリハビリが成立すると思っていました。
実際に働いてみると、成立しないことを痛感しました(-_-;)
成立しない理由は色々ありますが、他院との違いは、当院の患者様の多くが要介護高齢者のため、ご家族や支える施設職員さんなど、登場人物が多いことは1つあると思います。

平塚:
他職種スタッフとはどんな連携をするのでしょうか?
前田:
主に情報交換が多いです。
というのも情報交換をしないと、リハビリを行うときに自身が患者さんから聞く話とカルテの情報が情報の全てになってしまいます。
例えば、コミュニケーターがヒアリングして得たご本人のこれまでの人生の話。
退院担当の医療相談員に聞く、退院後に待っている生活環境や、ご家族の話。
訪問診療担当の医療相談員から聞いた、普段施設で過ごしている様子や施設の雰囲気など…
患者さん一人ひとりに対しての情報量は圧倒的に増えます!
平塚:
情報が増えることにより、どんなメリットを感じていますか?
前田:
患者さんのこれまでの人生や生活背景を知りながらリハビリテーションを行えるので、入院前後の繋がりを意識できるようになりました!
例えば、重症な心不全の患者さんが入院され担当した際、正直リハビリテーションで何が出来るのだろうと悩んだことがありました。
その時、コミュニケーターや医療相談員がご家族やご施設とコミュニケーションを取り、ご本人のことやご家族のお気持ち、退院後の生活環境をヒアリングしてくれました。
実は入院前まで歩けていて元気に過ごされていたそうで、ご家族はかなり落ち込まれていました。
コミュニケーターや担当の医療相談員と一緒にベストを模索し、徐々に状態も改善したため、面会時には元気な姿をご家族に見せたいと考え車椅子に乗る練習をしたり、精神賦活を図ったり。
退院後の生活環境から福祉用具の選択に悩んだりと、様々な視点からリハビリテーションを実施したことを覚えています。
結果的には、食事量が少なく、高齢者施設でのお看取りも見据えての退院になりましたが、退院後に少し食べれるようになったと聞き、リハビリテーションが退院後の生活につながったのかもしれないと感じました。
自分ひとりでは、ここまで考えられなかったし、やりきれなかったと思います。
【当院の地域連携】
平塚:
前田さんありがとうございました!
ふむふむ📝もう一つ生活回帰のキーワードとして、生活の場との連携、つまり地域との連携が大変重要になるのではないかと、思っております。
最後に高齢者施設への定期訪問を担当しご活躍されているセラピストの一人。
主任の西山さんに「地域連携」をテーマに主に高齢者施設との関わりについてお話いただきます。
西山:
当院では、理学療法士が月1回、定期的に訪問をしている高齢者施設が複数あります。
始めた経緯は、生活回帰のリハビリテーションを実現するためには、退院後の生活環境を知ることが必要と考え施設訪問をしたことがきっかけです。
実際に訪問してみると、高齢者施設で生活の面(介護)で様々な問題を抱えていることを知りました。
入所者様に対してはリハビリテーションの視点で。高齢者施設で働く職員さんに対しては、セラピストの知識や技術をアドバイスすることで、お役に立てるのではないかと考え取り組み始め、数年が経過しています。

平塚:
さすがベテランの西山さん!僕が聞きたいことをスラスラーと話してくださり助かります。
僕か質問しなくても記事が完成していまいそうです(笑)
実際やってみて、取り組む前と具体的どのような「違い」がありますか?
西山:
定期的に訪問することで、入院する前の状態から、退院したあとの生活まで繋がりを持ったリハビリテーションを行うことができるようになりました。
あとは定期訪問という接点ができたことで、自然と施設スタッフとのコミュニケーションも増え、情報交換も多くなったと思います。
例えば、入院前から定期訪問に行くと『また歩きたい。トイレに一人で行きたい』仰っていた方がいました。
入院の機会に評価し、ご本人の希望を少しでも叶えるために、担当セラピストと模索しました。
入院期間は2週間程度と短かったため、退院後も入院中のメニューを継続してもらえるよう調整を図り、施設のスタッフさんと情報共有を行いました。
退院後は、定期訪問でフォローをしつつ、徐々に出来ることが増えていったことをよく覚えています。
結果的にお一人でトイレに行けるようになり、今でも居室の壁に運動メニューを貼り、頑張っているんですよ。
高齢者の急性期リハビリテーションでは、リハビリテーションが退院後どのように繋がったのか、自分たちの仕事の良し悪しにあたる「結果」を得ることが難しい環境だと思います。
定期訪問によって「結果」を得られる環境はセラピストとして有難いです。
平塚:
高齢者施設からもこの取り組みは大変評価をいただいていると聞いてます。
“西山先生”なんて声を聞いたことがありますが、さらに仕事の魅力とか聞いてもよいでしょうか?
西山:
ありがとうございます。お恥ずかしながら、そのように呼んでくださる施設スタッフさんがいらっしゃいます💦
答えのない問題や初めて直面することもありますが、そのように頼ってもらっている以上、必ず応えたいと思いますし、僕のやりがい、モチベーションに繋がっています。
施設や病院単体では解決できないことも、そういった繋がりから医療も介護もみんなでカバーしていけたらいいなと。
いずれは自分たちも受ける介護ですから、この超高齢社会を地域みんなで明るくしていきたいと思います!

【まとめ】
平塚:
西山先生、ありがとうございました!
最後に結城さん、締めの言葉をお願いします!
結城:
はい、ここまでたくさんお話させていただきましたが…
当院で行っている“生活回帰”に向けたリハビリテーションには、他職種連携・地域連携が不可欠です。
というのも、その人らしい暮らしの実現には、たくさんの人の情報が必要だからです。
この記事をみて、湘南第一病院のリハビリテーション課を知り、興味をもってくださったら嬉しいです🎵
平塚くん、この度はリハビリテーション課のインタビューをしてくださりありがとうございました✨
以上、「当院のリハビリテーションと他職種連携・地域連携」をお届けしました。
取材を通して、他職種連携や地域連携は、医療機関では当たり前のもので、なぜ必要なのかその意味なんて考えたことなかったと気づかされました。
リハビリテーション課のみなさんがイキイキ仕事されている理由が見えてきた気がします👀
そんなリハビリテーション課では、一緒に働く仲間を募集しています。
理学療法士、作業療法士、セラピストのみなさん、興味をもってくださった方は、まずは一度ご見学にお越しください💨
『湘南で一番、高齢者にやさしい病院』で待っています!!